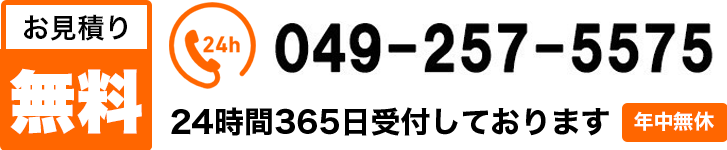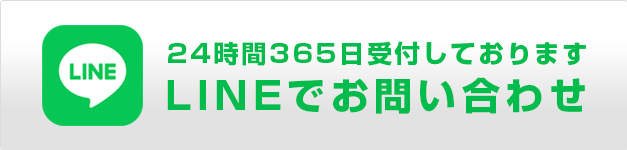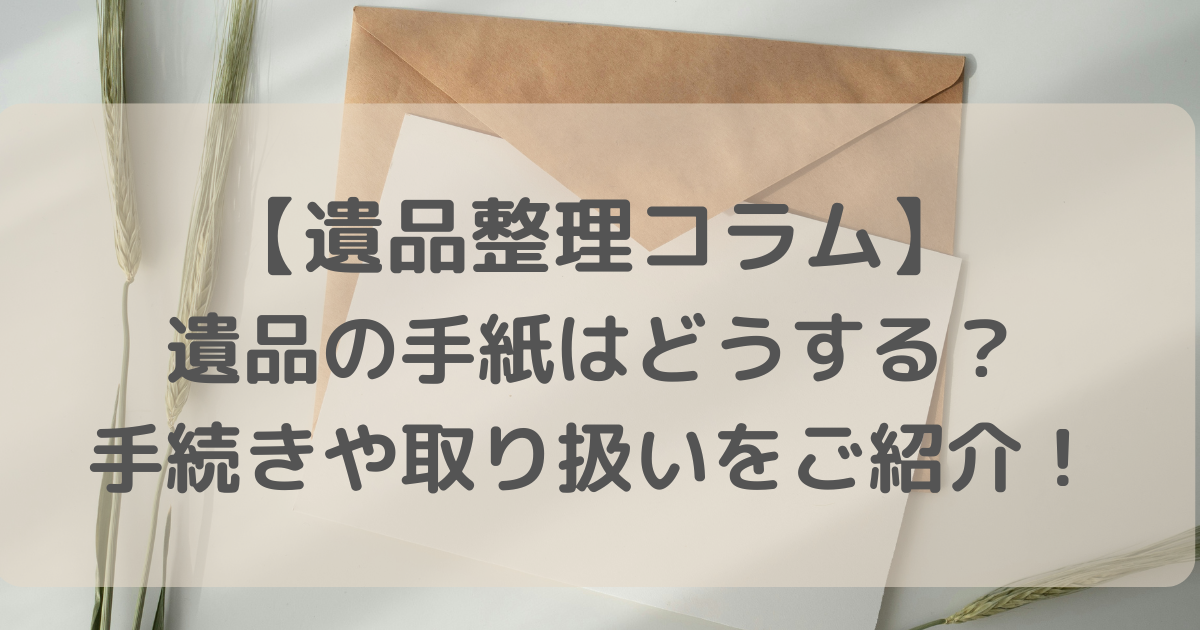
遺品整理をしていると故人様がしまっていた手紙が出てくるのはよくあることでしょう。
ご友人様に宛てた手紙や奥様、旦那様に想いを伝えたお手紙が出てくるようなドラマチックなこともあるかもしれません。
ただ、便箋1枚なら場所も取らないし、管理も楽だから保存するのもいいでしょう。
しかし、大量に出てきた場合やあまり喜べない手紙が出て来て困ってしまう場合もあります。
今回は遺品整理で出てきた手紙との向き合い方や適切な対処について、ご紹介していきます。
本題に入る前に、私たちについて簡単に自己紹介をいたします。
私たち遺品整理プロエールは埼玉県を中心に遺品整理業を請け負っています。
遺品整理の代表的な資格である遺品整理士に加え、遺品供養士やグリーフケアアドバイザー、終活カウンセラーといった専門的な資格を持つスタッフを多く抱えています。
実績と経験豊富な専門家目線で解説していくので、遺品整理について検討している方はぜひ、最後まで読んでみてください。
どんな手紙が出てくる?

遺品整理の中で出てくる手紙は役所や国からの通知など公的なものから友人、知人から受け取った私的なものまで様々です。
もちろん、遺品整理でタンスなどを開けて初めて貯めていたことを知る場合もあります。
まずは捨てたり、保存したりといった取り扱いの前に公的私的を問わず、手続きが必要なものと手続きの内容をご紹介します。
年金に関する通知

年金に関する通知は故人が高齢者だった場合、見かけることが多いです。
年金を受け取っている方が亡くなられた場合、親族が年金受給者死亡届を提出する必要があります。
提出が遅れると、死後も年金が振り込まれてしまい、不正受給となってしまう場合があります。
まだ手続きしていなかった場合は手続きをしておきましょう。
なお、年金とマイナンバーを連携している場合は自動的に処理されるため、手続きは必要ありません。
税金に関する通知

税金に関する通知の中でも未納の税金に対する督促状があった場合は手続きが必要となります。
納税期限が過ぎていないか、確認し、必要なら納税するのがいいでしょう。
また、税金に関する通知は故人様が亡くなられた年度だけでなく、翌年に届く場合もあります。
特に、事業主やシルバーワーカー、不動産などで収入があった場合、亡くなられた翌年に納税通知が届くため、遺産を相続した人が納税する必要があります。
なお、故人の遺産を相続している場合、住民税は故人の遺産からも支払いができます。
また、亡くなられて以降は故人様の収入は発生しないため、2度3度と故人様の住民税を支払う必要はありません。
ただし、故人の遺産の一切を相続せず、相続放棄していた場合は納税の義務が引き継がれないため、故人様の住民税の納付は必要ありません。
金融機関からの通知
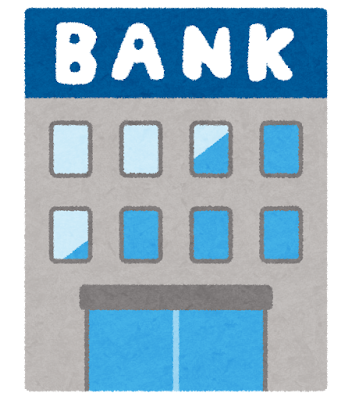
金融機関からの通知は主に通帳の記入や資産運用に関するものが大半です。
そのため、基本的には金融機関からの通知で手続きが必要なものは少ないです。
ただし、口座契約者が亡くなられた場合、金融機関に届け出る必要があります。
準備物や手続きについて詳しい説明が受けられるので、取引があったとわかる金融機関には連絡しておくといいでしょう。
なお、金融機関に連絡する前に故人様の口座から現金を引き出してしまうと相続の放棄ができなくなります。
相続の放棄を考えている場合は金融機関と連携しながら進めて行くのがいいでしょう。
ライフラインに関する通知
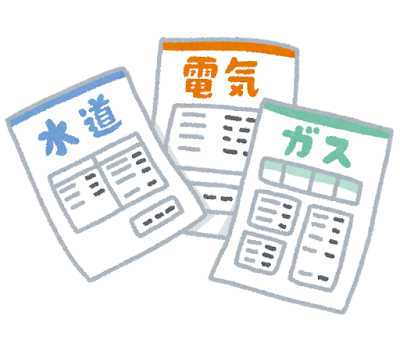
ガスや電気、水道などライフラインに関する通知も手続きが必要です。
故人様と同居していた場合は問題ないですが、故人様が一人で暮らしていた場合は電気や水道などの料金が発生する場合があります。
特に、故人様の住居を引き継いで生活しない場合は解約とともに発生している料金の支払いが必要になります。
また、忙しいからと放置すると追加で料金が発生する場合もあるため、なるべく早めに手続きするのがいいでしょう。
なお、各社小さな違いはあるものの、運転免許書などの本人確認や死亡届などが必要となります。
借金に関する通知
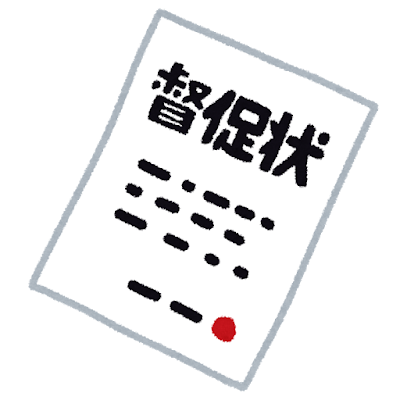
借金に関する通知が放置されている場合もあります。
特に未払いのまま支払期限を過ぎたことを連絡する督促状が金融機関やカード会社、消費者金融、弁護士事務所から届いていた場合は対処が必要です。
まずは通知を送ってきた相手に支払い状況を確認しましょう。
残っている借金に合わせて、すべてを相続する単純承認、部分的に相続する限定承認、そして、一切相続しない相続放棄から選択するのがいいでしょう。
ただし、無視していれば未納扱いで法的措置をとられるほか、債務者の死亡を伝えてから3か月で単純承認となってしまいます。
限定承認や相続放棄を選択したい場合は早めに決断するといいでしょう。
なお、借金返済のためでも故人の持ち物を売ってしまうと、相続の意思ありとみなされ、相続放棄ができなくなる場合もあり、注意が必要です。
ダイレクトメールや定期購読物
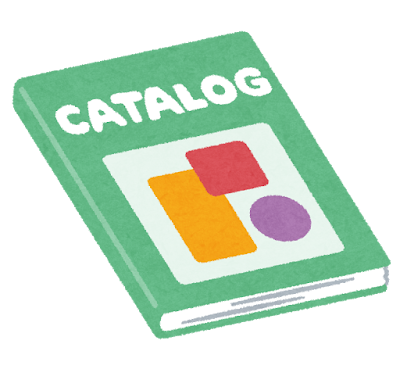
ダイレクトメールや通販カタログ、定期購読物も手続きしたい手紙です。
特にダイレクトメールは定期購読と違い、購読期間が終了しても送られ続ける場合があります。
また、定期購読の雑誌の中には自動で更新と引き落としを行う場合もあります。
通販カタログや定期購読の雑誌は発行元に連絡し、解約すれば送られてくることはなくなります。
ダイレクトメールについても開封せず、『受取拒絶』と書いた付箋を貼り付けて、配達員に渡すことで受け取りを拒絶できます。
なお、受取拒絶は配達員に直接渡すほか、郵便の窓口に持って行ったり、ポストに投函したりしても処理されます。
郵便配達の時間に都合がつきにくい場合は他の方法を利用するのもおすすめです。
故人様の手紙の取り扱い方
遺品を整理する中で出てきた故人様のお手紙のうち、手続きの必要がないお手紙の取り扱い方を3種類ご紹介します。
寺社でご供養する

故人様のお手紙を寺社に持ち込み、供養していただくお取り扱い方です。
ご供養では神主さんが祝詞を読んだり、和尚さんが読経したりする中、手紙などをお焚き上げし、供養します。
多くの寺社では定期的に合同でご供養しているため、日程を確認して持ち込むことで供養してもらうことができます。
ただし、寺社によって費用や日程、持ち込んでよい物や量が違うので、持ち込む前に確認する必要がある点は注意が必要でしょう。
ご供養は自宅でできる?

お焚き上げを行うのに十分な広さがあったとしても、ご供養は自宅でやらない方がいいです。
お焚き上げを自宅で行おうとした場合、焚き火でやろうとする方がほとんどかと思います。
しかし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、通称廃棄物処理法によりドラム缶や焚き火でごみを燃やす野焼き行為は禁止されています。
お焚き上げと野焼きでは感覚こそ違うものの、何も知らない方からすれば同じ『物を燃やす行為』であり、通報されれば罪に問われる可能性もあります。
もちろん、通報されなくても、煙による体調不良ややけど、火事などの危険もあるため、業者あるいは寺社に依頼するのがおすすめです。
もえるごみとして処分する

もえるごみとして処分するのが一番簡単です。
地域のゴミの日に出したり、クリーンセンターに持ち込んだりして、燃えるごみとして焼却してもらいます。
ただし、ごみの日に出す場合はそのまま捨てると個人情報が漏れてしまう心配があります。
そのため、手紙を裁断したり、住所を塗りつぶしたりしてから捨てるのがいいでしょう。
なお、クリーンセンターに持ち込む場合は持ち込む手間がある一方で、その場で焼却炉に投入できるため、プライバシーの心配が少ないです。
ダイレクトメールなど気持ちとして、軽いお手紙はもえるごみで処分するのがいいでしょう。
遺品整理業者に依頼する

遺品整理業者に依頼する場合、手紙以外の遺品の整理や処分を頼めるのがメリットです。
特に、遺品供養士やグリーフケアアドバイザーなど遺品整理の専門家が所属する行者は遺族の方のケアにも力を入れている場合が多いです。
手紙をはじめとする遺品整理をまとめて依頼できるのはもちろん、遺品の供養やグリーフケアにも精通しています。
重いタンスや運びようがない大きな棚など遺品整理で困っている方には特におすすめの取り扱い方です。
まとめ

今回は遺品整理の中で出てきた手紙について、ご紹介しました。
市役所や金融機関など友人や家族の他にも手紙はいろいろな関係の中で交わされます。
それだけに手紙をため込むタイプの方の場合、遺品整理の中でとんでもない量の手紙が出てくる場合もあります。
友人や家族など思い入れのある手紙はお焚き上げをして供養し、ダイレクトメールなど思い入れのない手紙はもえるごみとして片付けるのがおすすめです。
もし、遺品整理の作業や作業を始める前に引き出しや戸棚を開けてみたらたくさんの手紙があったという場合はぜひ、思い出してみてください。
お手紙の整理に限らず、遺品にまつわるお悩みを解決するお手伝いをいたします。
今回も遺品整理プロエールのお役立ちコラムを最後までお読み頂き、ありがとうございます。
最後に改めて、私たちの紹介をさせてください。
遺品整理プロエールは埼玉県を中心に関東地方で遺品整理業務を行い、年間7000件以上のご依頼実績があります。
また、当社は国内でも数少ない遺品整理士協会認定の優良事業認定事業社です。
遺品整理士はもちろん、遺品供養士やグリーフケアアドバイザー、終活カウンセラーと専門資格を持つスタッフが多数在籍し、一括で対応できる体制を整えています。
リサイクル可能なご遺品に関しては買取査定し、廃品の処理についても一括で対応できる用意をしております。
どこよりも丁寧に、安心安全をモットーにお客様の寄り添い感動頂けるサービスを業界最安値で提供させて頂きます。
もし、遺品整理でお悩みでしたらお気軽にご一報ください。
また、コラムの内容でご不明な点がある方やもっと詳しく話を聞きたい方はぜひ、お問い合わせください。
埼玉県対応地域一覧
さいたま市/川越市/熊谷市/川口市/行田市/秩父市/所沢市/飯能市/加須市/本庄市/東松山市/春日部市/狭山市/羽生市/鴻巣市/深谷市/上尾市/草加市/越谷市/蕨市/戸田市/入間市/朝霞市/志木市/和光市/新座市/桶川市/久喜市/北本市/八潮市/富士見市/三郷市/蓮田市/坂戸市/幸手市/鶴ヶ島市/日高市/吉川市/ふじみ野市/白岡市/伊奈町/三芳町/毛呂山町/越生町/滑川町/嵐山町/小川町/川島町/吉見町/鳩山町/ときがわ町/横瀬町/皆野町/長瀞町/小鹿野町/東秩父村/美里町/神川町/上里町/寄居町/宮代町/杉戸町/松伏町
東京都対応地域一覧
千代田区/中央区/港区/新宿区文京区/台東区/墨田区/江東区/品川区/目黒区/大田区/世田谷区/渋谷区/中野区/杉並区/豊島区/北区/荒川区/板橋区/練馬区/足立区/葛飾区/江戸川区/八王子市/立川市/武蔵野市/三鷹市/青梅市/府中市/昭島市/調布市/町田市/小金井市/小平市日野市/東村山市/国分寺市/国立市/福生市/狛江市/東大和市/清瀬市/東久留米市/武蔵村山市/多摩市/稲城市/羽村市/あきる野市/西東京市/瑞穂町/日の出町/檜原村/奥多摩町/大島町/利島村/新島村/神津島村/三宅村/御蔵島村/八丈町/青ヶ島村/小笠原村
神奈川県対応地域一覧
横浜市/川崎市/相模原市/横須賀市/平塚市/鎌倉市/藤沢市/小田原市/茅ヶ崎市/逗子市/三浦市/秦野市/厚木市大和市/伊勢原市/海老名市/座間市/南足柄市/綾瀬市/葉山町/寒川町/大磯町/二宮町/中井町/大井町/松田町/山北町/開成町/箱根町/真鶴町/湯河原町/愛川町/清川村/
千葉県対応地域一覧
千葉市/銚子市/市川市/船橋市/館山市/木更津市/松戸市/野田市/茂原市/成田市/佐倉市/東金市/旭市/習志野市/柏市/勝浦市/市原市/流山市/八千代市/我孫子市/鴨川市/鎌ケ谷市/君津市/富津市/浦安市/四街道市/袖ケ浦市/八街市/印西市/白井市/富里市/南房総市/匝瑳市/香取市/山武市/いすみ市/大網白里市/酒々井町/栄町/神崎町/多古町/東庄町/九十九里町/芝山町/横芝光町/一宮町/睦沢町/長生村/白子町/長柄町/長南町/大多喜町/御宿町/鋸南町/